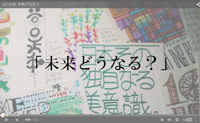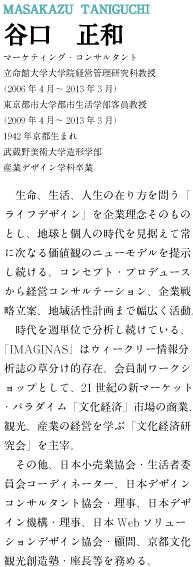 
|
2016年12月26日 ガロという時代
私は1970年3月号でガロの新人賞に「タイトルはありません」で入賞し、発表の場を得た。
ガロは発表と評価の役割に先鞭をつけ、横丁文化として、裏道クラブ的マーケットそのものの中に複合していた。
青林堂という小さな編集室に何度か訪問し、ガロの初代編集長 長井勝一さんには「あんまり焦って走らないほうがいい」など多くのアドバイスをいただいたのを覚えている。
当時から文化の表通りというより裏通りにあった雑誌だった。寺山修司や唐十郎に代表されるような、メインシアターではなくテントを劇場そのものと見切る美学。そこが劇場だと思えば劇場になる。
内にこもらずに、書を捨て町へ出よと寺山が呼びかけた時代。
佐々木マキや林静一などと同世代で、私は漫画家にはならなかったが、文化の裏道が探り当てたアンチテーゼのように見えながら、もう一つ先の文化に明るさを投げかけるような気配に、次の時代を想像していた。
創刊50年を超えて、「ガロ」のフィードバックブック『ガロという時代』(青林堂 税別1800円)が出版されている。
伝統的なサブカルチャー、コミックカルチャーの楔を引き受けてきた劇画の、ミニ劇場と呼べるような繰り返しは、我々の中に泥臭さ、土の匂い、表を歩けなかった人への目線を思い起こさせる。積み残された人々に共感の目線を持っただろうかという教訓をそこに見る。時代は多彩と多様性に流れがあり、ガロはそこに至る勇気を与えた。
私は1970年3月号でガロの新人賞に「タイトルはありません」で入賞し、発表の場を得た。 ガロは発表と評価の役割に先鞭をつけ、横丁文化として、裏道クラブ的マーケットそのものの中に複合していた。 青林堂という小さな編集室に何度か訪問し、ガロの初代編集長 長井勝一さんには「あんまり焦って走らないほうがいい」など多くのアドバイスをいただいたのを覚えている。 当時から文化の表通りというより裏通りにあった雑誌だった。寺山修司や唐十郎に代表されるような、メインシアターではなくテントを劇場そのものと見切る美学。そこが劇場だと思えば劇場になる。 内にこもらずに、書を捨て町へ出よと寺山が呼びかけた時代。 佐々木マキや林静一などと同世代で、私は漫画家にはならなかったが、文化の裏道が探り当てたアンチテーゼのように見えながら、もう一つ先の文化に明るさを投げかけるような気配に、次の時代を想像していた。 創刊50年を超えて、「ガロ」のフィードバックブック『ガロという時代』(青林堂 税別1800円)が出版されている。

伝統的なサブカルチャー、コミックカルチャーの楔を引き受けてきた劇画の、ミニ劇場と呼べるような繰り返しは、我々の中に泥臭さ、土の匂い、表を歩けなかった人への目線を思い起こさせる。積み残された人々に共感の目線を持っただろうかという教訓をそこに見る。時代は多彩と多様性に流れがあり、ガロはそこに至る勇気を与えた。
2016年12月20日 きもの文化と日本
伊藤元重さんは東京大学名誉教授、学習院でも教授を務め日本の経済学を引っ張ってきたオピニオン、「やまと」代表取締役会長 矢嶋孝敏さんはアパレルも含め呉服業界を牽引されてきたオピニオン。
『きもの文化と日本』(日本経済新聞出版社 税別870円)では、この二人が日本の生活文化への回帰が今高い生活性を帯びているということについて語り合っている。
日本人が独自性と個性を問いかけて足元に目線を置いたとき、着物は織りや染めを超えて四季とともに培ってきた日本の独自文化を象徴するひとつの領域として、ウェアラブルという点における世界への広がりを持っている。
民族衣装に込められた文化としての高い伝承性と、個性を求める今日性。これらが重なりあい顕在化している。
昔の着物を復活させるわけではなく、独自性への回帰を考えたときに自ずと顔を出す存在感。その重要性を、生活の中の着物という切り口で編集している。
さらに言うなら、成長から成熟へという流れがそこにはあり、小さくてもいいので自然と共生する生活文化村の中に複合している。漠然とした伝統回帰ではなく、地産地消、手作りするご近所の里山、より自立項目の高い流れを生活の中に持っている。この本は着物文化マーケティングの新しい姿を果敢にリポートしている。
伊藤元重さんは東京大学名誉教授、学習院でも教授を務め日本の経済学を引っ張ってきたオピニオン、「やまと」代表取締役会長 矢嶋孝敏さんはアパレルも含め呉服業界を牽引されてきたオピニオン。 『きもの文化と日本』(日本経済新聞出版社 税別870円)では、この二人が日本の生活文化への回帰が今高い生活性を帯びているということについて語り合っている。

日本人が独自性と個性を問いかけて足元に目線を置いたとき、着物は織りや染めを超えて四季とともに培ってきた日本の独自文化を象徴するひとつの領域として、ウェアラブルという点における世界への広がりを持っている。 民族衣装に込められた文化としての高い伝承性と、個性を求める今日性。これらが重なりあい顕在化している。 昔の着物を復活させるわけではなく、独自性への回帰を考えたときに自ずと顔を出す存在感。その重要性を、生活の中の着物という切り口で編集している。 さらに言うなら、成長から成熟へという流れがそこにはあり、小さくてもいいので自然と共生する生活文化村の中に複合している。漠然とした伝統回帰ではなく、地産地消、手作りするご近所の里山、より自立項目の高い流れを生活の中に持っている。この本は着物文化マーケティングの新しい姿を果敢にリポートしている。
2016年12月12日 リバーバンクリポート
新潟長岡市の新しい社会と都市のデザインに対して学習し、取材をし共有する。そのような意味合いでの未来学習と情報共有のためのメディア「リバーバンクリポート」を興し、編集人を引き受けている樋口栄治さんと、アートディレクションを手がける福田毅さんは私の友人である。
地域ルネサンスの認識の中で、この雑誌は創刊された。今回は私も寄稿させていただいている。
見えざる文化と経済ということを軸足に、21世紀のヒントと構想を書かせていただいているが、大事な点は共学の仕組みを持ち、情報という変化を様々なところで受信し、共感していくことだ。それが分析というものであり、目標設定のところに優れた価値観認識、未来像を注入するためのメディアであることを高く評価したい。
今日SNSを使ったネットワークの中で、嘘も本当も入り混じるという指摘もあるが、情報というものはまず仮説があってそれを検証する過程で生まれる変化そのものである。先に夢があり観測気球のように上がったものが未来への創造力となるのであり、既に出来上がったものの告知ではない。重要なことはビジョンメイキングをリーダーシップとして強く学習し実体化に影響を与ることであり、タイムラグがあったにせよ実態は後から付いてくる。
そのような意味合いの中で、このリバーバンクリポートは次なる創造に向けて重要な意味合いがあると確信しており、ここにエールを送りたい。
新潟長岡市の新しい社会と都市のデザインに対して学習し、取材をし共有する。そのような意味合いでの未来学習と情報共有のためのメディア「リバーバンクリポート」を興し、編集人を引き受けている樋口栄治さんと、アートディレクションを手がける福田毅さんは私の友人である。
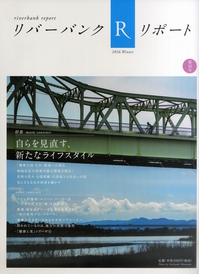
地域ルネサンスの認識の中で、この雑誌は創刊された。今回は私も寄稿させていただいている。 見えざる文化と経済ということを軸足に、21世紀のヒントと構想を書かせていただいているが、大事な点は共学の仕組みを持ち、情報という変化を様々なところで受信し、共感していくことだ。それが分析というものであり、目標設定のところに優れた価値観認識、未来像を注入するためのメディアであることを高く評価したい。 今日SNSを使ったネットワークの中で、嘘も本当も入り混じるという指摘もあるが、情報というものはまず仮説があってそれを検証する過程で生まれる変化そのものである。先に夢があり観測気球のように上がったものが未来への創造力となるのであり、既に出来上がったものの告知ではない。重要なことはビジョンメイキングをリーダーシップとして強く学習し実体化に影響を与ることであり、タイムラグがあったにせよ実態は後から付いてくる。 そのような意味合いの中で、このリバーバンクリポートは次なる創造に向けて重要な意味合いがあると確信しており、ここにエールを送りたい。
2016年12月 5日 凛女の選択
女性が自らの生き方として立脚点を明らかにし、仕事を通して牽引力を発揮する。男女がクロスする社会の良さを生かすには、女性たちが活躍のリーディングをとり、立ち上がる女性とそれを推す男性というところまでモデルを作ることが必要だと思う。
【画像】
凛女シリーズの第2弾、生き方編ということで、この度『凛女の選択』(税別1500円)が週刊住宅新聞社より出版された。人生における社会的な関係構築についてをテーマとしている。凛女推進委員から執筆者24名をはじめ監修、編集に至るまでをメンバー全員で参加するスタイルで進められている。注目すべきは、あふれる想いの編集力にある。
この企画をリードしているのが立命館のMBAの初代卒業生、萩原実紀さんで優秀な教え子の一人である。いろんな意味合いの中で生き方こそが、最も重要な個性の拠り所であり、意欲と貢献の柱ということをよく心得ている。
女性が自らの生き方として立脚点を明らかにし、仕事を通して牽引力を発揮する。男女がクロスする社会の良さを生かすには、女性たちが活躍のリーディングをとり、立ち上がる女性とそれを推す男性というところまでモデルを作ることが必要だと思う。

凛女シリーズの第2弾、生き方編ということで、この度『凛女の選択』(税別1500円)が週刊住宅新聞社より出版された。人生における社会的な関係構築についてをテーマとしている。凛女推進委員から執筆者24名をはじめ監修、編集に至るまでをメンバー全員で参加するスタイルで進められている。注目すべきは、あふれる想いの編集力にある。 この企画をリードしているのが立命館のMBAの初代卒業生、萩原実紀さんで優秀な教え子の一人である。いろんな意味合いの中で生き方こそが、最も重要な個性の拠り所であり、意欲と貢献の柱ということをよく心得ている。
|