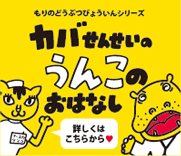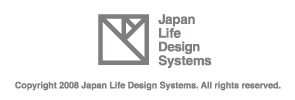2012.9.18更新
サントリー美術館
「お伽草子(おとぎぞうし)
この国は物語にあふれている」
内覧会に行ってきました!
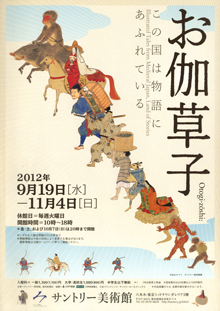
「お伽草子 この国は物語にあふれている」展
会期/2012年9月19日(水)~11月4日(日)
休館日/火曜日
開館時間/10時~18時
ただし金・土、および10月7日(日)は20時まで
いずれも入館は閉館の30分前まで
入場料/一般1300円 大学・高校生/1000円 中学生以下/無料
場所/サントリー美術館
住所/東京都港区赤坂9-7-4 六本木・東京ミッドタウン ガレリア3階
Tel.03(3479)8600 http://suntory.jp/SMA/
東京・六本木のサントリー美術館で
明日から開催される「お伽草子」展。
絵本の研究プロジェクトとして
日本の絵本の原点を再確認したいと思い、
本日、ひと足早く内覧会に行ってきました。
絵と文字で物語を楽しむ文化は
平安時代に始まったそうです。
とりわけ室町時代から江戸初期にあたる
14世紀から17世紀にかけては、
新しい物語が次々に生まれ、
絵巻や絵本のかたちで広く親しまれたのです。
それらを称して「お伽草子」と呼びます。
その総数は400種を超えるとか。
その中には、私たちがよく知っている
『一寸法師』や『浦島太郎』などもあります。
-thumb-515x341-7974.jpg)
図録の表紙見開きです。
絵柄は「百鬼夜行絵巻(ひゃっきやぎょうえまき)」。
室町時代(16世紀)の京都・真珠庵の作品。
重要文化財。
長年、人間に奉仕してきたさまざまな道具たちが
用済みとなり捨てられたのを恨んで
妖怪に化けて練り歩く。
人気の絵巻だったらしく、室町時代から江戸時代にかけて
60作品以上が作られたそうです。
道具が妖怪になるという奇想天外なストーリー、
大胆な構図、要所要所で目をひく着彩など
今見てもとても新鮮で迫力のある作品です。
 「お伽草子展」ポスター裏面より。
「お伽草子展」ポスター裏面より。
右上の絵は、「浦島絵巻」。
16世紀の作品です。
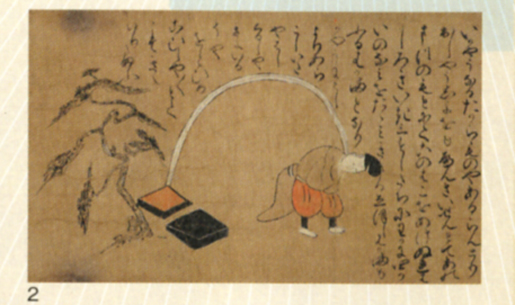
「浦島絵巻」の部分を拡大してみました。
浦島太郎が玉手箱をあけた瞬間、
煙がでてきて老人に変身してしまうシーン。
当時は上記のような、白い弓なりの線による表現が
せいいっぱいだったとの解説がありました。
なお、「浦島太郎」という名前になったのは後世になってから。
この絵が描かれていた16世紀には、
「浦島子(うらしまこ)」という名前でした。
図録に掲載されていた解説文によると
お伽草子は次の6種類に分類されるそうです。
①公家物語
②僧侶・宗教物語
③武家物語
④庶民物語
⑤異国・異郷物語
⑥異類物語
この中でとくに注目したいのが⑥の異類物語。
これは、動植物や器物を主人公とする作品群で、
昔の文化人たちの自由奔放なイマジネーション炸裂!
といった感じでとても楽しいのです。
その代表的な作品が絵本となって
ミュージアム・ショップで販売されていました。
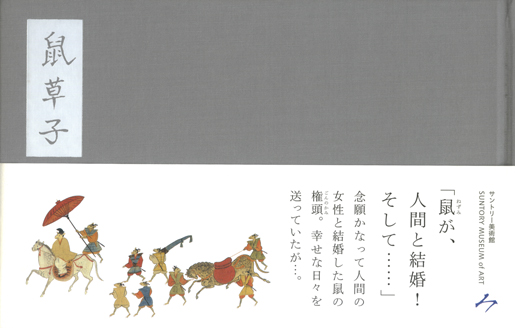
サントリー美術館 絵本シリーズ第一弾
『鼠草子(ねずみのそうし)』
編集・発行/サントリー美術館
裏の帯には、「絵巻に書かれた言葉を現代語訳して
昔の人の絵巻の楽しみ方を再現しました。
絵巻を読むように、絵本を楽しんでください。」
と書かれています。
オリジナルの『鼠草子絵巻』は
室町~桃山時代(16世紀)の作品。
畜生道を断ち切ろうと、人間の姫との結婚を企てた
ねずみの権頭(ごんのかみ)の物語。
展示会場では音声ガイドプログラムを搭載した機材の
貸し出しもあり、音声ガイドマークのある作品のところで
簡単な操作をすると、ヘッドホンを通して物語のあらすじや
時代背景などの解説が流れてきます。
要所要所、全部で20作品の解説が聞けるので分かりやすく、
また、前述の分類とは別に
「お伽草子にはなぜ清水寺がよく登場するのか」
といった興味深いお話も聞けたりして、絶対におすすめです♪
そして、全体を通して印象的だった2点について。
まず一つ目は、主人公が夢に破れ、恋に破れ
大いなる挫折を味わったり反省したりすると、
最後ほとんどが「出家」して終わるところ。
もうちょっと「現世」でがんばってほしいな!
なんて思うのは私だけでしょうか!?
あまりにも「出家しました」で終わるのが続いて、
昔はそれが唯一の救いの道だったとはいえ
あまりにも切なく衝撃的でした。
二つ目は、『しぐれ絵巻』という
女流絵師の描いた1513年の作品。
この作品では、左大臣の息子・中将さねあきらをはじめ
身分の高い男性たちはみな
二重まぶたに描かれていたこと!
(女性たちは、いわゆる平安の美人顔の一重まぶたなのに!)
まるで現代の少女漫画と同じ感覚です。
”イケメン”だと、当時でも二重だったんだ~!
と、これまた目ウロコ的発見でした。

『しぐれ絵巻』に登場するやんごとなき男衆の
二重まぶたに注目!
(図録より抜粋)
いずれにしても、ふだんとは違った視点から
絵本の楽しさを感じた展覧会でした。
お伽草子の世界から、
文化の秋をいちはやく味わってみませんか?! (ミヤタ)

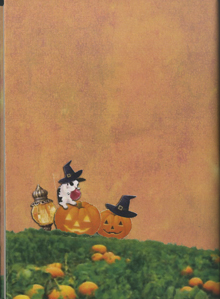

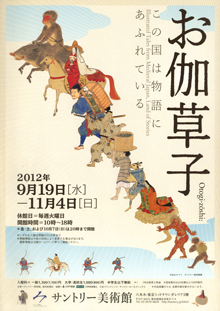
-thumb-515x341-7974.jpg)

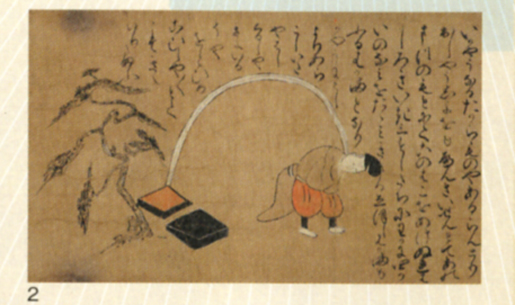
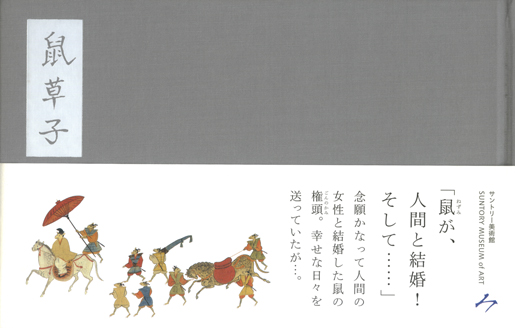

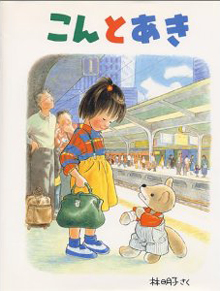 林 明子/作 福音館書店/刊
林 明子/作 福音館書店/刊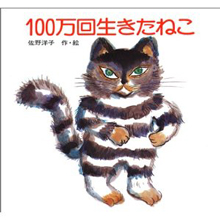 佐野洋子/作 講談社/刊
佐野洋子/作 講談社/刊