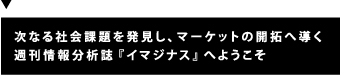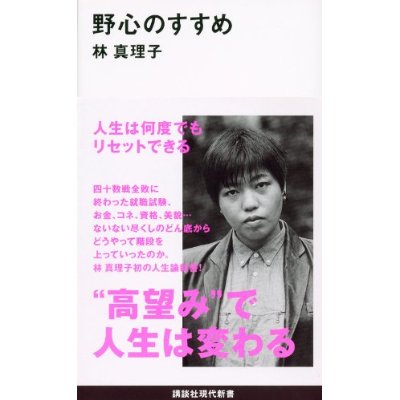
第一章、最初の副題は
『屈辱感は野心の入り口』。
紹介されるのはまだ三流のコピーライターだった彼女のエピソード。
『二流、三流の人達は自分たちだけでかたまりがち』
と言う彼女は、
『三流の仲間と新宿に飲みに行っては業界の大スターだった糸井重里のことを「糸井はさー」なんて言ってクダを巻いて』いたそう。
『誰も糸井さんにお会いしたことが無かったくせに。一番恥ずかしい時代です』
とその時を振り返っている。
気の合う仲間と居るのはとても良いことだが、実は危険でもあるということが解る。
とりわけ、一緒に居て楽な相手というのは自分に引け目を感じさせる部分の無い人間、つまり自分と同レベルかあるいはそれ以下の相手ということがある。全てのケースがそうではないが、自分と同じようなレベルの人間で周りを固めて余りにも居心地の良いコミュニティを作ってしまえば一生そこから抜け出せない、抜け出そうという気持ちにすらならない危険性を含んでいる。
そんな心地よい日々につかりきっていた彼女の耳に、コピーライター養成学校に居た同期が東京コピーライターズクラブの新人賞を取ったというニュースが飛び込んでくる。
『いつものようにダラダラ過ごしていた会社で、同期の受賞を不意に知った時のまるで呼吸が止まってしまうような感覚』を知り、自分のだらしない現状を本気で何とかしようと考えて糸井重里のコピーライター講座に通い始めたのだという。
自分と同じ場所に居たはずの人間が、一流の世界へ歩を進めていくのを目の当たりにして突きつけられる「自分は三流」であるという事実。
そこで三流仲間と一緒に飲むことで溜飲を下げず、実際に現状を変えるための行動に移した点は当時の右肩上がりの時代背景も手伝ったのかもしれない。
今の日本人は屈辱感を屈辱感として素直に受け止める「屈辱の感受性」が発達しているのだろうか。FacebookやTwitterに自分の愚痴や怒りを書き綴って友達から「いいね!」と言ってもらうことで、下手をすれば大抵の屈辱感は解消できてしまう。
屈辱感の対処法を与えられてしまったということは、実は向上のエネルギーをも上手く削ぎ落とされているような気がしてならない。
『若い頃はバックパッカーでエコノミークラスに乗って旅行をした二人が、中年になってまた旅行をしようという事になったとして、片方は相変わらずエコノミークラスだけど、もう片方はビジネスクラスだと、気まずい空気が旅行のしょっぱなから漂うことになる。エコノミークラスにだけ乗っていれば、エコノミークラスだけしか目にしない。でもビジネスクラスはファーストクラスを通過しなければ席にたどり着けないのでファーストクラスという世界を目の当たりにすることになる』
YouTubeだけで満足していれば、一生YoutTubeだけ見て「本物」を知らないまま。
でも一度でも上質のエンターテインメントを生で体感すれば、YouTubeでタダで手に入る満足感以上の高揚感を知ってしまえば、それは立派な向上への原動力となりえる。経済・文化的な面においてもこの本の主張は単なる成功者の自慢話にはない示唆に富んでいる。
この本が出版されたのは2014年の4月。アベノミクスによる経済刺激とこの本のバブリーな示唆はリンクしていたのかもしれない。