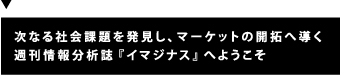今週のIMAGINAS分析会議では日経ビジネス7月19日号より以下の事例が報告された。
「個人の行動や発言がインターネットに蓄積されている。この残像は相続できる所有物か家族に対しても秘匿されるべきものか。国家はこれを覗けるのか。その難しい判断は今、企業に委ねられている。
4月16日の旅客船セウォル号の沈没事故。なくなった高校生チェ・ソンホくんの母、オさんは息子の16年の軌跡を見つめて過ごしている。息子が残したもの全てを見て存在を感じたい、という理由で彼が利用していたスマートフォン向けメッセンジャーソフト「カカオトーク」の記録の開示を問い合わせたが、カカオは開示を拒んだ。
しかし、オさんのもとに一通の手紙が届く。送り主は事故対応も満足にできなかった海洋警察庁。中に入っていた書類には、事故前後の息子のカカオトークや携帯電話の通信記録を閲覧したという通知。事前の承諾は無く、オさんの手は怒りに震えた。なぜ国は息子のデータを勝手に見るのに、遺族は見れないのか
LINEも同じで、時々自殺者の家族から個人の自殺の理由を知りたいが為の開示の要求が舞い込むが、一切の開示には応じていない」
谷口は以下のようにコメント。
「死者の情報。残像の記憶。デリケートな問題だな。ベネッセの個人情報漏洩問題と通じるものがある。企業は個人情報をあまりにも保有しすぎている」
息子の残した少しの情報でも手に入れたいと願う母親の気持ちを考えるととても耐えられない。
谷口の言った、ベネッセの個人情報流出という問題も事例の出来事に絡んでいる。
我々は企業に何らかの個人情報を預ける際に、
「個人情報は国家などの申請以外では開示せず、厳格に保管します」
という告知を企業から受ける。
それ故に、事例にあるLINEやカカオなどの企業の対応には正当性がある。
例えば契約者がまだ生存している場合は家族や親族といえどもその情報を本人に無断で開示することはプライバシーの侵害に当たる。
しかし、契約者が死亡した場合は正に企業内に残された記憶は「残像」のように足場の無い曖昧なものになってしまう。
ベネッセの件でも、谷口は
「企業が余にも膨大な個人情報を抱えるのはいかがなものか」
という考えを示している。
死者の個人情報に焦点を当てるのではなく、個人情報を企業が管理することの是非をもう一度問い直す時期にさしかかっているのかもしれない。
インターネットや情報サービスが一般家庭に根付いてまだ20年にも満たない。
個人情報という概念に至っては騒がれ始めたのはここ数年のことだ。
真に問題となっているのは何なのか。根本的な議論が求められている。